医療DXがもたらす未来

近年、デジタル技術の進化により、医療分野におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)が急速に進展しています。医療分野におけるDXとしては、電子カルテやAI診断、遠隔医療などを駆使して医療の効率化と質の向上を図るのが主な取り組みといえます。
ここでは医療DXの現状と今後の展望について考察していきたいと思います。
医療DXとは
医療DXとは、保健・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書等の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)において発生する情報やデータを、全体最適された基盤(クラウドなど)を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えることです。(引用:厚生労働省「医療DXについて」)
厚生労働省が策定した「医療DX令和ビジョン2030」は、医療の未来像を描いており、以下の以下のように語られております。

厚生労働省「医療DX令和ビジョン2030」の概要
このビジョンは、デジタル技術を活用した医療の未来を見据え、患者にとっての利便性を高めるとともに、医療従事者の業務負担を軽減することを目的としています。具体的には次の施策が提案されています。

- 電子カルテの普及促進:すべての医療機関で電子カルテを導入し、インターネット接続も可能にし医療データの一元管理を実現することで、情報の共有とアクセスの迅速化を図ります。(まだ紙カルテで運用している医療機関や、電子カルテを導入済みだがオンプレ型サーバで運用している医療機関が多く、また端末ごとにデータ管理されており、データ連携がスムーズに行えていない)
- クラウド化促進:病院の情報システム(電子カルテ、レセコン、部門システム等)関連経費増削減、システム関連人材不足を解消していく。(クラウド化することにより、システム連携がしやすくなり、結果的に業務効率化、負担軽減につながる)
- マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化の推進:受給者証の紙発行廃止、医療保険の資格情報及び受給者証情報の手動入力の削減、資格過誤請求の減少、医療費助成の資格確認に関する事務負担や自治体への照会が減少。受給者証忘れによる償還払いの事務も減少。患者本人の薬剤や診療のデータに基づくより良い医療の提供が図られる。
- 自治体検診事務のデジタル化:マイナンバーカード1枚で検診を受診可能。紙廃止による、事務作業軽減を図る。
- 生成AI等の診断支援システムの導入:生成AI等の技術を活用して、診断の精度向上や治療方針の選定を支援するシステムを広めることで、医療の質を大幅に向上させます。、生成AI等の最新技術やサービスを活用する上でもクラウド化を進めていく。
- 遠隔医療の拡充:地理的な制約を超え、患者が自宅で専門医の診療を受けられる体制を整え、医療アクセスの向上を図る。
- ビッグデータ解析の活用:医療データを駆使して、予防医療や健康管理の新たな手法を創出し、より効果的な治療や予防策を実施する。
(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001380624.pdf)
医療DXの重要性
これらの施策を通じて、医療DXは単なる技術革新にとどまらず、医療現場における業務効率化や質の向上を求められています。
具体的には、電子カルテの導入によって医療情報の迅速な伝達が可能となり診療の流れをスムーズにし、AI診断支援システムでは医師の判断をサポートし、診断の精度を高めることで患者への適切な治療を迅速に提供できるよう取り組まれております。
さらに、遠隔医療の拡充により患者は自宅から専門医の診療を受けることができ、地域的な医療格差の是正にも寄与されるので、特に高齢者や移動が困難な患者にとって、この仕組みは非常に重要であると考えられます。

業界への影響
医療DXの推進は医療従事者にとっても大きなメリットをもたらすと考えられ、医療DXにより業務効率が向上することで、医師や看護師はより多くの時間を患者ケアに充てることができ、結果的に医療の質が向上すると言われています。
また、医療従事者の働き方改革にもつながり、職場環境の改善や労働時間の短縮を実現する可能性があると考えられます。
医療DXを進める理由
医療DXの推進は、単なる技術革新にとどまらず、社会的課題の解決に直結する重要な取り組みです。具体的な社会的課題は、以下です。
- 地方では医療機関が不足し、専門医の確保も困難です。特にへき地では、高度な医療を受けることが難しい状況があります。
- 医師や看護師の長時間労働や業務の煩雑さが問題となっています。特に、紙のカルテや手作業による業務が多く、業務効率が低下しています。
- 高齢化に伴い、医療費が増加し、国の財政負担が深刻化しています。
- 災害時には医療機関が被災し、迅速な診療が困難になります。
- 医療機関ごとにデータが分断され、診療情報の共有が不十分であるため、適切な治療が受けられないケースが発生しています。
(参考資料)
- 厚生労働省
第1回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム資料について
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/000992373.pdf - デジタル庁
自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)
https://www.digital.go.jp/policies/health/public-medical-hub - 経済産業省「ヘルスケア産業政策」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/01metihealthcarepolicy.pdf - 総務省「ICTを活用した医療・介護の現状と課題」
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc266120.html
日本では高齢化が進行し、医療ニーズの増大に対して医療従事者が不足しているという現実があります。また、医療費の増加は国家財政を圧迫しており、効率的な医療提供体制の構築が求められています。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックを通じて、遠隔医療やオンライン診療の必要性が再認識されました。患者が病院に足を運ばずに適切な診療を受けられる仕組みを整えることは、感染症対策や医療の地域格差を是正する上でも極めて重要です。
さらに、総務省が医療機関で長年利用されてきた院内PHSの廃止を検討しており、これが医療DX推進の一因ともなっています。

高度なデジタルコミュニケーションツールに移行することによるメリット
- 場所を選ばず、全国どこでも利用可能。
- チャットアプリを活用し、スムーズなコミュニケーションの実現
- 患者情報や電子カルテをリアルタイムで確認可能
- ビデオ通話による遠隔相談
- 夜間のオンコール対応
- スタッフの位置情報も見ることができる
医療機関におけるスマートフォン導入は、単なる通信手段の変化ではなく、業務の効率化や患者対応の迅速化、セキュリティ強化といった大きなメリットをもたらします。現在、国内の多くの病院でこの移行が進められており、医療DXの重要な一環として位置づけられています。
PHSが医療現場における連絡手段として広く使われてきましたが、サービス終了が決まれば、より高度なデジタルコミュニケーションツールへの移行が必要です。
Wi-Fiや5Gを活用したスマートデバイスの導入が進むことで、医療スタッフ間のリアルタイムな情報共有が可能になり、 業務の効率化や迅速な意思決定につながります。このような変化に対応するためにも、医療DXの導入は避けられない流れとなっています。

日本の医療現場の状況

【医師の長時間労働】
厚生労働省の調査によると、病院に常勤する男性医師の41%、女性医師の28%が週60時間以上勤務しています。
【医師の働き方改革の施行】
2024年4月に医師の働き方改革が施行され、時間外労働の上限が年間960時間、月平均80時間、単月100時間未満に設定されました。
【医療DX推進体制整備加算の見直し】
2025年4月1日から、マイナンバーカードの保険証利用率や電子処方箋の導入状況に応じて、初診料等に加算される点数が変更される予定です。
(参考資料)
- 厚生労働省「医師の勤務実態等について」
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000173612.pdf?utm_source=chatgpt.com - 厚生労働省「医師の働き方改革 手続きガイド」
https://www.mhlw.go.jp/content/001115352.pdf?utm_source=chatgpt.com - 厚生労働省「医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001277499.pdf?utm_source=chatgpt.com
医療DXの費用対効果

導入コスト:医療DXの導入には初期投資が必要ですが、長期的にはコスト削減や業務効率化、医療の質の向上が期待されます。
電子カルテやデジタルツールの購入には一定のコストがかかりますが、将来的には医療業界全体のコスト削減につながると予想されています。
業務効率化:電子カルテやAI診断支援システムによって診療や事務作業の効率化が進み、医療従事者の負担軽減が期待されます。
医療の質の向上:遠隔医療やビッグデータ解析の活用により、患者への迅速かつ適切な医療提供が可能となり、診療の質が向上します。
- オンライン診療システムの導入
取り組み内容:患者が自宅から医師に相談できるオンライン診療プラットフォームを導入。
成功要因:新型コロナウイルスの影響でオンライン診療の需要が急増し、患者の時間と移動コストを削減。
費用対効果:患者の通院が減少し、医療機関の待機時間やリソースの効率化が図られることで、経済的負担も軽減されます。 - AI画像診断システムの導入
取り組み内容:AIを活用してがんや肺疾患の早期発見を支援する画像診断システムを導入。
成功要因:診断時間を大幅に短縮(1件あたり15分→5分)し、診断精度が医師単独よりも10%向上。
費用対効果:診断の迅速化により、早期治療が可能となり、患者の健康維持や医療コストの削減に寄与。 - 統合型医療情報システムの導入
取り組み内容:各診療科でバラバラだったシステムを統合し、患者データを一元管理。
成功要因:診療情報の共有がスムーズになり、患者の待ち時間が20%減少。
費用対効果:業務の効率化により、医療従事者の労働時間を削減し、サービスの質向上にも寄与。
(参考資料)
- 医療DXの導入事例・メリット・デメリットを徹底解説!日本と海外の最新動向も紹介
https://xrcloud.jp/blog/articles/business/7030/ - 【2025年最新】医療DX事例7選|成功要因やボトルネックについて徹底解説
https://ops-in.com/blog/%E3%80%902025%E5%B9%B4%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%80%91%E5%8C%BB%E7%99%82dx%E4%BA%8B%E4%BE%8B7%E9%81%B8%EF%BD%9C%E6%88%90%E5%8A%9F%E8%A6%81%E5%9B%A0%E3%82%84%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%83/ - 医療DXの現状と重要性
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsrpim/36/1/36_79/_article/-char/ja
国からの補助金
医療業界に対する補助金
- 運営費交付金
国立病院や医療研究機関に対する運営資金が提供され、これにより質の高い医療サービスの提供が促進される。 - 施設整備費補助金
医療機関の施設整備を支援するために、改修や新設に対する補助が行われ、医療環境の向上が図られている。 - 研究開発資金
医薬品や医療機器の開発に向けた研究に対して助成が行われ、革新的な医療技術の開発が促進される。
介護福祉業界に対する補助金
- 介護保険事業費補助金
介護サービスの提供を支援するために、介護保険制度を通じて資金が支給され、特に高齢者向けの福祉サービスが強化される。 - 人材育成支援
介護職員の研修や教育に対して助成が行われ、質の高い介護を提供できる人材の育成が図られている。 - 施設整備補助金
介護施設の新設や改修に対する補助が提供され、利用者がより快適に過ごせる環境が整備されている。
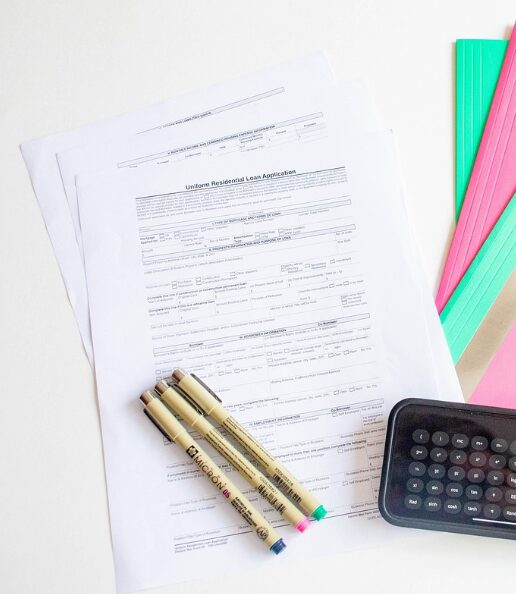
医療DXについて、懸念される課題やリスク
- データセキュリティとプライバシーのリスク
医療データは非常にセンシティブな情報であり、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが高まります。データが不正アクセスされると、患者のプライバシーが侵害されるだけでなく、医療機関の信頼性も損なわれる可能性があります。 - 技術的な不均衡
医療機関間でのITインフラやデジタルリテラシーの差が存在し、特に地方や小規模な医療機関ではDXの導入が遅れる可能性があります。これにより、サービスの質にバラつきが生じ、地域格差が拡大するリスクがあります。 - コストの増大
初期投資や運用コストが高く、特に中小医療機関にとっては経済的負担が大きくなることがあります。これがDX導入の障壁となり、医療サービスの全体的な効率化が進まない可能性があります。 - 人材不足
DXを推進するためには、ITスキルを持つ人材が必要ですが、医療業界においてはそのような人材が不足している状況があります。これにより、技術の導入や運用がスムーズに行かないリスクが生じます。 - 医療従事者の抵抗感
新しい技術やシステムに対する医療従事者の抵抗感や不安感がある場合、DXの進行が妨げられることがあります。教育やトレーニングを行わなければ、効果的な活用が難しくなります。 - 規制や法制度の整備
医療DXに関する法制度や規制が整備されていない場合、企業や医療機関が新たなサービスを展開する際に法的な不安が残ることがあります。特にデータの扱いや使用に関する法令遵守が求められます。 - 品質管理の課題
デジタル化が進む中で、医療サービスの質を維持するための評価基準や管理手法が整備されていない場合、サービスの質が低下するリスクが考えられます。

赤字経営の病院の医療DX化について
- 優先順位の設定
•ニーズの特定:限られた予算で最も影響が大きい分野を特定し、優先順位を設定します。例えば、業務効率化や患者サービスの向上に直結する分野を最初にDX化することが考えられます。
•小規模な導入から開始:大規模なDXプロジェクトを一度に実施するのではなく、小規模なプロジェクトから始め、効果を測定しながら段階的に拡大するアプローチが有効です。 - 助成金や補助金の活用
•公的資金の申請:厚生労働省や地方自治体からの助成金や補助金が存在します。医療DXに特化した補助金を調査し、申請することで資金を得ることができます。
•民間の助成プログラム:一部の民間企業や団体も医療DXを支援するための資金やプログラムを提供しています。これらを利用することで資金繰りの改善が期待できます。 - パートナーシップの形成
• IT企業との連携:医療DXの専門家やIT企業とパートナーシップを組むことで、技術的な支援やコスト削減の可能性を探ることができます。特に、成果報酬型の契約を検討することで初期投資を抑えられる場合があります。
• 地域の医療機関との協力:複数の医療機関が協力して共同でDXを進めることで、コストを分担し、リソースを有効に活用することができます。 - 業務プロセスの見直し
• 無駄の排除:DXを進める前に、現在の業務プロセスを見直し、無駄な業務やコストを削減します。業務の効率化がDXの基盤となります。
• デジタルツールの導入:手軽に導入できるデジタルツール(業務管理ソフト、電子カルテ、オンライン予約システムなど)を選定し、少ない投資で業務改善を図ります。 - 従業員の教育とエンゲージメント
• 社内研修の実施:DXに関する教育を行い、従業員のデジタルリテラシーを向上させることで、DX化を円滑に進めることができます。従業員が新しいシステムに対して前向きになるよう、成功事例を共有することも重要です。
• 意識の変革:DXの意義や利点を従業員に理解させ、全員がプロジェクトに参加する意識を持つことが成功の鍵です。 - データ活用による収益の最大化
• データ分析の活用:患者データや業務データを分析し、収益向上に繋がる戦略を立てることができます。例えば、患者のニーズに基づいた新しいサービスの提供や、効率的なリソース配分を行うことで収益改善が期待できます。 - 長期的な視点での投資
• ROIの評価:DXにかかるコストと期待されるリターン(ROI)を詳細に評価し、長期的な視点で投資を行うことが重要です。短期的な利益だけでなく、長期的な効率性や患者満足度の向上も考慮します。

今後の展望
医療DXのさらなる発展には、テクノロジーと人間の協働が不可欠です。AIが医師の意思決定を支援する「AI診療支援システム」や、患者のバイタルデータをリアルタイムで解析する「ウェアラブルデバイス」の普及が期待されています。
また、5G通信技術の発展により、遠隔医療の精度と利便性が向上し、都市部と地方の医療格差を縮小する可能性があります。これにより、過疎地域に住む患者でも都市部の専門医の診察を受けやすくなるでしょう。加えて、クラウドネイティブ技術の活用も医療DXの鍵となります。クラウドネイティブとは、クラウド環境を前提に設計されたアプリケーションやシステムで、医療データの安全な管理や迅速なアクセスを可能にします。これにより、病院間のデータ共有やリアルタイムでの診療情報の更新がスムーズに行えるようになります。
さらに、NTTが提唱する「IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)」の技術は、超低遅延かつ大容量の通信を実現し、医療DXの進展を加速させる可能性があります。たとえば、遠隔手術の精度向上や、大規模な医療データのリアルタイム分析が可能になり、より高度な医療サービスの提供が期待されます。

医療DXは、医療の質を向上させるだけでなく、医療従事者の負担軽減や病院経営のコスト削減にも寄与する可能性があります。今後も技術革新と制度の整備を進め、持続可能な医療システムを構築していくことが求められます。
今後の日本の医療業界は、高齢化社会の進展や技術革新、政策の変化により大きな変革を迎えることが予想されます。まず、高齢化の影響で在宅医療や慢性疾患管理のニーズが高まる中、医療機関は患者が自宅で質の高い医療を受けられる体制を構築する必要があります。また、AIやデータ分析の導入が進むことで、診断の精度向上や業務の効率化が図られ、医療の質が一層高まるでしょう。さらに、地域包括ケアシステムが進展し、医療と介護の連携が強化されることで、地域住民の健康を支えるサービス提供が求められます。
新たなビジネスモデルとしては、健康管理や予防医療のサービスが注目され、医療機関はこれに対応したプログラムやサービスを展開することで収益を多様化させることができるでしょう。医療従事者の育成においては、多様な人材の採用と継続的な教育が重要であり、ICTスキルを持つ人材の確保が競争力の鍵となります。さらに、医療制度や政策の変化に迅速に適応し、持続可能な経営を実現するための戦略が不可欠です。このように、医療業界は今後、患者中心のサービスを重視しつつ、効率性や質の向上を追求していくことが求められます。

